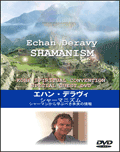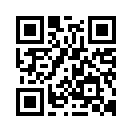2010年03月18日
地球巡礼者─アースピルグリム(5-1) 地球と人類の調和
今回の章は、今までの章の中で最も多くのメッセージが含まれており、かつ、文明の中で生きる私達にとっては「掴みづらいもの」という印象を受けました。
それだけ非常に深く、潜在的に含まれた意味がある──そう感じたのです。
今回、私は記事にまとめるのが「とても難しい」──そう思いました。
この章の中には「巡礼者として生きる在り方」と「シャーマンという、自然と宇宙に直結した存在」の両者が描かれていたからです。
そこで悩んだ結果、この章に関しては「巡礼者として生きる在り方」と「シャーマンの(自然と共に生きる)在り方」の二つに分けることにしました。
今回は、「巡礼者として生きる在り方──地球と人類の調和」について、記事にしたいと思います。
一番最初の解説で、私は「この地球巡礼者という映画そのものが、土着した民族性である日本人に理解出来るか疑問だった」と書きましたが、今回の章はそれが如実に描かれていました。
しかし、「だからこそ」──この章は、私達にとって「とても大切な章なのだ」と、そう思えるのです。
前回の章では「太陽系そのものが巡礼している」という問題提起──すなわち「生命の在り方そのものが、巡礼という方式の中にあるのではないか」という疑義が描かれていました。
そして、今回の章ではその前の章(3)にある「世界的な危機」、および(4)の「環境への適応と、生命そのものが巡礼者であることを受け入れることによる進化」を複合させ、「その答え」を模索する為「ペルーの巡礼の旅」が描かれています。
ペルーの巡礼、そしてペルーの人達が感じる自然への畏敬に関し、レネ・フランコ・サラスはこのように語っています。
「私たちは祖先の伝統を継承しています。祖先は自然を敬い、大切に守ってきました。山やジャングルからやって来た彼らは、母なる大地”パチャママ”に畏敬の念を抱いていました。”パチャママ”は、神でも人でもありません。宇宙に存在する万物の完全なる調和です。太陽も月も、その一部です」
「神でも、人でもない」──。
ここに、ペルーの人達独特の「信仰心」があるように思いました。
要するに、彼らが祈っているのは利益や繁栄の為ではなく、共存と調和の為なのだ──と。
もしかしたら、私たち文明人の考え方と「最も違う」のは、その点なのかもしれません。
「人類に調和が訪れることを祈るのであれば、まず最初に、自らの内なる調和を見つけることから始めれば良い」
ナレーターの語る言葉に、私達が求めなければならない姿勢が示唆されているのかもしれません。
レネ・フランコ・サラスは語ります。
「この巡礼は”星と雪の祭り(ルビ・コイヨリッティ)”と呼ばれています。生命と自然を敬い、感謝する一種の形式に過ぎません。すべての生物に生命を与え、維持する要素がここにあります。(中略)
ここアンデスの社会には、自然の秩序が存在します。”アイニ”というバランスを保つ方法です。”アイニ”とは、お互いに助け合い、分け合い、他人のために尽くすシステムなのです」
自然と共存しあう人達は、大地も、草木も、すべては「生きている神聖な存在」として見ています。しかし、私達文明人にとってそれは「物質のひとつ」でしかありません。
地球も「ただの鉱物」──そうとしか思っていない科学者や地質学者は、大勢いることでしょう。
しかし、すべてが「生命である」──そういう視点に立ち返ることで、私達は多くの気づきと、今ある危機の回避と、同時に「何が過ちだったのか」に、気づける謙虚さを持てるかもしれません。
アプ・コイヨリッティという、とても高い山の頂きにある「氷」を取りにいく巡礼に、エハン・デラヴィとスタッフは参加しました。
そこには毎年、6万にも及ぶ人達が巡礼に訪れるそうです。とても過酷な、高山の道をひたすら登り続ける巡礼。
彼らを突き動かすのは、ひとえに「信仰心」であり、そこにはいっさいの疑念も猜疑心もないのです。
ここにある宗教は「スペインに侵攻された歴史」が物語るかのように、キリスト教と水を信仰する先住民の民俗宗教が合致したものです。
これを見れば、「宗教は形ではないし、祈る対象が問題なのではない」ことが、お分かり頂けるはずです。
宗教に必要なのは、形式ではなく──「信仰心」それだけなのだ、ということが。
周りの環境に感謝し、与えられていることに感謝出来る──それこそが、大切なのだということも。
地球巡礼者──。
これは、ただひとつのテーマだけで語れない「壮大な内容なのだ」ということを、私は実感せずにいられませんでした。
地球巡礼──すなわち「今まで地球が経てきた歴史」イコール「人類が犯してきた過ち」をも、振り返らないことには話を進められないからです。
だからこそ、私はウェイド・デイヴィスの言葉が印象的でした。
「原住民は、環境の変化は自分たちの責任だと考えます。これは悲劇的なことです。"ヒマラヤ"や"アンデス"の人々は地球は生きていると信じ、山の神の存在を信じています。物事がゆがめば、自分の問題ととらえます。
最も胸が痛くなる一例が、コイヨリッティなのです。
伝統的に見ると、先住民族の宗教文化とキリスト教文化の融合です。アンデス世界をよく表しています。インカの文化と同様に、カトリックの影響を受けているのです。
巡礼は神聖なる活動になります。地域から持ってきた十字架を担いで登り、シナカラを見下ろす氷河の頂に、それを打ち立て、一晩置いてパワーを注入し持ち帰ります。
昔は氷のかたまりも持ち帰っていたのですが、氷河の危機を知ってからは、持ち帰らなくなりました。自分たちの責任だと思っているのです。氷河から削られた氷のかたまりは、巡礼に参加できない人のために持ち帰られていたのです。それは溶ける量に比べればごく僅かです。
人間の大量虐殺は、必ず非難を受けますが、直接的でも間接的でも、民族文化の破壊は非難されません。むしろ"発展途上"の問題として推奨されているのが現状です。
人類学の世界にいる人間は、民族文化を閉じこめることは勧めません。博物館用の生きた標本ではないのですから。
"変化"は文化の脅威ではありません。
すべての文化が、変化を受け入れてきました。テクノロジーは脅威の対象ではないです。インターネットは自由を与えるツールとして、世界的に人に力を与えてくれるのです。ラコタ族が弓矢をライフルに持ち替えても、ラコタ族に変わりはありません。私たちが、馬車を車に変えても、人種は変化しないのと同じです。文化は繊細で壊れやすく、"消えゆく運命"だと考えるのは正しくありません。
変化や技術ではなく、権力に脅かされているのです」
この言葉──。私達日本人も、聞いていて苦しくなるのではないでしょうか?
私達の文化は、今、どこにあるのでしょう。
着物を着ている人が、街をどれだけ歩いているでしょうか? 畳の上で、正座をして暮らしている人が、どれだけいるでしょうか?
文化はいつしか「ファッション」となり、日本人特有の文化であった「道(茶道・剣道・柔道)」も、ただの作法になり果てている──。
文化──。
失ってはいけないものが、日本の中で失われつつあります。
私達は戦争ですべてを失った後、高度経済成長やバブル期を経て豊かになったものの、「もっと大切だった日本人の精神性」を失ってしまったのかもしれない──そんなふうに思わずにいられませんでした。
ウェイド・デイヴィスは、とても大切な言葉で締めくくっています。
「著書にも書きましたが、望みは残されています。文化を破壊するのは人間ですが、しかし人間は、保存の促進もできるのです。この"破壊"のプロセスは、自然界から起きるものだとすれば、まったく何もできない。
しかし、決してそうでないから選択が可能です。
先住民の文化を昔のままに固定しないで、逆に、どういう生活をしたいのかを自問し、すべての民族の経験と知識を集め、多くを学べる多文化の世界をどうやって築いていくかを考えることです」
この文化の在り方については、日本人も決して他人事ではないはずです。
もしかしたら──未来の地球では民族、血縁、人種いっさい関係なく「文化による棲み分け」が、行われているかもしれませんね(笑)。
DVD「地球巡礼者」絶賛発売中。(すでにお持ちの方は、これからの解説も踏まえて視聴して頂けましたら幸甚です。何度みても必要なメッセージが、この中に含まれている──私はそう感じました。)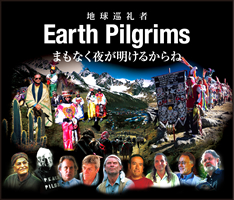
エハン・デラヴィ最期のトークイベントも受付中です。
17年間の研究成果すべてを聞けるラストチャンスです。

YOU are EARTH 篠崎由羅
それだけ非常に深く、潜在的に含まれた意味がある──そう感じたのです。
今回、私は記事にまとめるのが「とても難しい」──そう思いました。
この章の中には「巡礼者として生きる在り方」と「シャーマンという、自然と宇宙に直結した存在」の両者が描かれていたからです。
そこで悩んだ結果、この章に関しては「巡礼者として生きる在り方」と「シャーマンの(自然と共に生きる)在り方」の二つに分けることにしました。
今回は、「巡礼者として生きる在り方──地球と人類の調和」について、記事にしたいと思います。
一番最初の解説で、私は「この地球巡礼者という映画そのものが、土着した民族性である日本人に理解出来るか疑問だった」と書きましたが、今回の章はそれが如実に描かれていました。
しかし、「だからこそ」──この章は、私達にとって「とても大切な章なのだ」と、そう思えるのです。
前回の章では「太陽系そのものが巡礼している」という問題提起──すなわち「生命の在り方そのものが、巡礼という方式の中にあるのではないか」という疑義が描かれていました。
そして、今回の章ではその前の章(3)にある「世界的な危機」、および(4)の「環境への適応と、生命そのものが巡礼者であることを受け入れることによる進化」を複合させ、「その答え」を模索する為「ペルーの巡礼の旅」が描かれています。
ペルーの巡礼、そしてペルーの人達が感じる自然への畏敬に関し、レネ・フランコ・サラスはこのように語っています。
「私たちは祖先の伝統を継承しています。祖先は自然を敬い、大切に守ってきました。山やジャングルからやって来た彼らは、母なる大地”パチャママ”に畏敬の念を抱いていました。”パチャママ”は、神でも人でもありません。宇宙に存在する万物の完全なる調和です。太陽も月も、その一部です」
「神でも、人でもない」──。
ここに、ペルーの人達独特の「信仰心」があるように思いました。
要するに、彼らが祈っているのは利益や繁栄の為ではなく、共存と調和の為なのだ──と。
もしかしたら、私たち文明人の考え方と「最も違う」のは、その点なのかもしれません。
「人類に調和が訪れることを祈るのであれば、まず最初に、自らの内なる調和を見つけることから始めれば良い」
ナレーターの語る言葉に、私達が求めなければならない姿勢が示唆されているのかもしれません。
レネ・フランコ・サラスは語ります。
「この巡礼は”星と雪の祭り(ルビ・コイヨリッティ)”と呼ばれています。生命と自然を敬い、感謝する一種の形式に過ぎません。すべての生物に生命を与え、維持する要素がここにあります。(中略)
ここアンデスの社会には、自然の秩序が存在します。”アイニ”というバランスを保つ方法です。”アイニ”とは、お互いに助け合い、分け合い、他人のために尽くすシステムなのです」
自然と共存しあう人達は、大地も、草木も、すべては「生きている神聖な存在」として見ています。しかし、私達文明人にとってそれは「物質のひとつ」でしかありません。
地球も「ただの鉱物」──そうとしか思っていない科学者や地質学者は、大勢いることでしょう。
しかし、すべてが「生命である」──そういう視点に立ち返ることで、私達は多くの気づきと、今ある危機の回避と、同時に「何が過ちだったのか」に、気づける謙虚さを持てるかもしれません。
アプ・コイヨリッティという、とても高い山の頂きにある「氷」を取りにいく巡礼に、エハン・デラヴィとスタッフは参加しました。
そこには毎年、6万にも及ぶ人達が巡礼に訪れるそうです。とても過酷な、高山の道をひたすら登り続ける巡礼。
彼らを突き動かすのは、ひとえに「信仰心」であり、そこにはいっさいの疑念も猜疑心もないのです。
ここにある宗教は「スペインに侵攻された歴史」が物語るかのように、キリスト教と水を信仰する先住民の民俗宗教が合致したものです。
これを見れば、「宗教は形ではないし、祈る対象が問題なのではない」ことが、お分かり頂けるはずです。
宗教に必要なのは、形式ではなく──「信仰心」それだけなのだ、ということが。
周りの環境に感謝し、与えられていることに感謝出来る──それこそが、大切なのだということも。
地球巡礼者──。
これは、ただひとつのテーマだけで語れない「壮大な内容なのだ」ということを、私は実感せずにいられませんでした。
地球巡礼──すなわち「今まで地球が経てきた歴史」イコール「人類が犯してきた過ち」をも、振り返らないことには話を進められないからです。
だからこそ、私はウェイド・デイヴィスの言葉が印象的でした。
「原住民は、環境の変化は自分たちの責任だと考えます。これは悲劇的なことです。"ヒマラヤ"や"アンデス"の人々は地球は生きていると信じ、山の神の存在を信じています。物事がゆがめば、自分の問題ととらえます。
最も胸が痛くなる一例が、コイヨリッティなのです。
伝統的に見ると、先住民族の宗教文化とキリスト教文化の融合です。アンデス世界をよく表しています。インカの文化と同様に、カトリックの影響を受けているのです。
巡礼は神聖なる活動になります。地域から持ってきた十字架を担いで登り、シナカラを見下ろす氷河の頂に、それを打ち立て、一晩置いてパワーを注入し持ち帰ります。
昔は氷のかたまりも持ち帰っていたのですが、氷河の危機を知ってからは、持ち帰らなくなりました。自分たちの責任だと思っているのです。氷河から削られた氷のかたまりは、巡礼に参加できない人のために持ち帰られていたのです。それは溶ける量に比べればごく僅かです。
人間の大量虐殺は、必ず非難を受けますが、直接的でも間接的でも、民族文化の破壊は非難されません。むしろ"発展途上"の問題として推奨されているのが現状です。
人類学の世界にいる人間は、民族文化を閉じこめることは勧めません。博物館用の生きた標本ではないのですから。
"変化"は文化の脅威ではありません。
すべての文化が、変化を受け入れてきました。テクノロジーは脅威の対象ではないです。インターネットは自由を与えるツールとして、世界的に人に力を与えてくれるのです。ラコタ族が弓矢をライフルに持ち替えても、ラコタ族に変わりはありません。私たちが、馬車を車に変えても、人種は変化しないのと同じです。文化は繊細で壊れやすく、"消えゆく運命"だと考えるのは正しくありません。
変化や技術ではなく、権力に脅かされているのです」
この言葉──。私達日本人も、聞いていて苦しくなるのではないでしょうか?
私達の文化は、今、どこにあるのでしょう。
着物を着ている人が、街をどれだけ歩いているでしょうか? 畳の上で、正座をして暮らしている人が、どれだけいるでしょうか?
文化はいつしか「ファッション」となり、日本人特有の文化であった「道(茶道・剣道・柔道)」も、ただの作法になり果てている──。
文化──。
失ってはいけないものが、日本の中で失われつつあります。
私達は戦争ですべてを失った後、高度経済成長やバブル期を経て豊かになったものの、「もっと大切だった日本人の精神性」を失ってしまったのかもしれない──そんなふうに思わずにいられませんでした。
ウェイド・デイヴィスは、とても大切な言葉で締めくくっています。
「著書にも書きましたが、望みは残されています。文化を破壊するのは人間ですが、しかし人間は、保存の促進もできるのです。この"破壊"のプロセスは、自然界から起きるものだとすれば、まったく何もできない。
しかし、決してそうでないから選択が可能です。
先住民の文化を昔のままに固定しないで、逆に、どういう生活をしたいのかを自問し、すべての民族の経験と知識を集め、多くを学べる多文化の世界をどうやって築いていくかを考えることです」
この文化の在り方については、日本人も決して他人事ではないはずです。
もしかしたら──未来の地球では民族、血縁、人種いっさい関係なく「文化による棲み分け」が、行われているかもしれませんね(笑)。
DVD「地球巡礼者」絶賛発売中。(すでにお持ちの方は、これからの解説も踏まえて視聴して頂けましたら幸甚です。何度みても必要なメッセージが、この中に含まれている──私はそう感じました。)
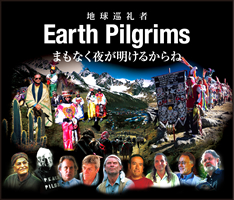
エハン・デラヴィ最期のトークイベントも受付中です。
17年間の研究成果すべてを聞けるラストチャンスです。

YOU are EARTH 篠崎由羅
Posted by エハン at 23:20