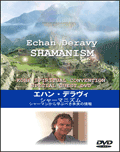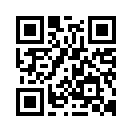2010年03月22日
地球巡礼者─アースピルグリム(5-2)自然と人を繋ぐ存在
かつては自然(自然神)信仰だった日本も、仏教が入ってくることでその在り方が変わってしまいました。しかし本来、日本文化の中には「自然を敬う姿勢」というのが少なからず入っていた──私はそう思います。
そのひとつに、「季節感を重んじる心」というのがあります。その季節にあった行事、風習を日本人は楽しみます。少なくとも、そこには「自然を資源とだけしかみない」という在り方はないはずです。
日本が精神的に崩れ始めてしまったのは、そうした「自然と一体化した生活」というものから切り離されて来たからではないか──そんなふうに思うこともあります。
今では旬も何も関係なく、どんな野菜や果物もスーパーで買えてしまう時代。そのうち「旬」という言葉さえ、死語に近くなってしまうかもしれない──。
これは「文明の力」といって褒め称えるべきものではなく、むしろ「自然から切り離されていく行為」として、嘆き悲しむべきものなのではないでしょうか。
レネ・フランコ・サラスの言葉は印象的です。
「星は兄弟で、丘と神聖な山(ルビ・アプ)は、私たちの保護者なのです。湖は、私たちに生命を与え、生活を支える祖父です」
完全に自然と一体化して生きられる姿勢というのを失ってしまった私たちにとって、レネの言葉は「自分たちの生活を省みる機会」をも与えてくれます。
また、この章の中でグラハム・ハンコックが語った言葉も印象的です。
「しかし、異次元世界を体験したいなら、シャーマンに会うのが一番です。彼らは日常生活の一部として、異次元世界を探索しているからです。
産業化し、技術の進んだ国で暮らす私たちは、シャーマンと比べて未熟です。私たちの文化は技術面では優れていますが、魂の探索という面においては著しく劣っていると思います。本当の意味で巡礼者になりたいのであれば、シャーマンに教えを請うべきです」
シャーマン。自然と共にあり、自然の智慧を授かる存在──。
本当に大切な智慧は人間が生み出した学問の中にはなく、大自然や宇宙の中にこそあるものなのかもしれません。
自然から切り離されて、自然をただの物質的現象と捉え、机上の空論を翳すことは可能でしょう。
しかし、人はいざ自然から切り離された状態で「本当の自然の智慧を授かることは出来ないのではないか」そうも思います。
だとしたら、私たちは文明が進めば進む程、生み出す知識は「自然や宇宙の法則から切り離された『ひとりよがりのもの』」となってしまう危険性は否めません。
シャーマン研究家のポール・テンプルは語ります。
「彼らは、私たちの健康状態を感じ取ります。肉体的な領域と精神的な領域のバランスが崩れたり、相対的世界に固執しすぎると、体のバランスが崩れます。どんな状況であっても、病気になるのです。シャーマンの所に行って癒しや浄化が必要だと言えば、吐き気や便意を催す薬草をくれます。まずは浄化して、それだけで肉体と精神のバランスを取り戻せるかを試すのです。
シャーマンにこの薬草のことをドラッグだと言えば、『それは全然違う』と答えるでしょう。『それは君たちの世界観の思いこみだ』と。この薬草はニューワールドのモノであって、異次元世界をつなぐ植物だから、『聖なる』植物として扱わなければならない。サボテンを鍋に入れて何時間も煮込んでいる間に、効果を高めるために良い気を入れることが重要だ。なぜなら、私たちは今世代の聖なる植物の番人だからです。この伝統を継承しているからです。だからこの伝統を尊敬し、大切にしましょう」
私たちはただの「思いこみ」で、何千年も続いてきた伝統を安易に壊したり、否定します。
しかし、「ならば私たちの文明は本当に正しいのか」と言えば──全くもって、そうではありません。
きっとこのペルーの地では、鬱病になった人に対して「大量の薬」が処方されることはないでしょう。
いえ、それどころか鬱病にさえかかることがないかもしれない。その事実だけで、充分「私たちの文明の問題点」が分かるような気がしてきます。
巡礼を前に、ワシューマと呼ばれる飲み物を飲んで儀式を行います。そうすることで、その地の自然との繋がりが強くなるからです。
原住民やシャーマンといった人々は、「いかに人間にとって、自然との繋がりが大切か」を知っている人たちのように思います。
それは「生命の本質」に近い在り方であって、エゴによって自然を支配しようとしている文明人の在り方とはほど遠い。いわば、「共存共栄」であり「調和しあう姿勢」だと、私には思えます。
そうした彼らの在り方を見ると、「文明というものは、人間の進化の産物と呼べるのか」──私は疑問です。
技術が便利になったところで、生物が退化してしまえば「まったくもって意味がない」。明らかに、私たち先進諸国の人たちは肉体的な意味でも、また精神的な意味でも退化してしまっているのではないでしょうか。
シャーマンや原住民の生き方は、私たちに「これからの人類は、どのように自然と共に生きていけばよいのか」という問題を提議してくれている──そんなふうにも感じる次第です。
DVD「地球巡礼者」絶賛発売中。(すでにお持ちの方は、これからの解説も踏まえて視聴して頂けましたら幸甚です。何度みても必要なメッセージが、この中に含まれている──私はそう感じました。)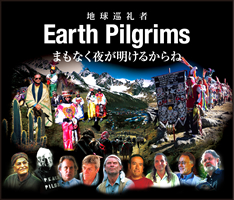
エハン・デラヴィ最期のトークイベントも受付中です。
17年間の研究成果すべてを聞けるラストチャンスです。

YOU are EARTH 篠崎由羅
そのひとつに、「季節感を重んじる心」というのがあります。その季節にあった行事、風習を日本人は楽しみます。少なくとも、そこには「自然を資源とだけしかみない」という在り方はないはずです。
日本が精神的に崩れ始めてしまったのは、そうした「自然と一体化した生活」というものから切り離されて来たからではないか──そんなふうに思うこともあります。
今では旬も何も関係なく、どんな野菜や果物もスーパーで買えてしまう時代。そのうち「旬」という言葉さえ、死語に近くなってしまうかもしれない──。
これは「文明の力」といって褒め称えるべきものではなく、むしろ「自然から切り離されていく行為」として、嘆き悲しむべきものなのではないでしょうか。
レネ・フランコ・サラスの言葉は印象的です。
「星は兄弟で、丘と神聖な山(ルビ・アプ)は、私たちの保護者なのです。湖は、私たちに生命を与え、生活を支える祖父です」
完全に自然と一体化して生きられる姿勢というのを失ってしまった私たちにとって、レネの言葉は「自分たちの生活を省みる機会」をも与えてくれます。
また、この章の中でグラハム・ハンコックが語った言葉も印象的です。
「しかし、異次元世界を体験したいなら、シャーマンに会うのが一番です。彼らは日常生活の一部として、異次元世界を探索しているからです。
産業化し、技術の進んだ国で暮らす私たちは、シャーマンと比べて未熟です。私たちの文化は技術面では優れていますが、魂の探索という面においては著しく劣っていると思います。本当の意味で巡礼者になりたいのであれば、シャーマンに教えを請うべきです」
シャーマン。自然と共にあり、自然の智慧を授かる存在──。
本当に大切な智慧は人間が生み出した学問の中にはなく、大自然や宇宙の中にこそあるものなのかもしれません。
自然から切り離されて、自然をただの物質的現象と捉え、机上の空論を翳すことは可能でしょう。
しかし、人はいざ自然から切り離された状態で「本当の自然の智慧を授かることは出来ないのではないか」そうも思います。
だとしたら、私たちは文明が進めば進む程、生み出す知識は「自然や宇宙の法則から切り離された『ひとりよがりのもの』」となってしまう危険性は否めません。
シャーマン研究家のポール・テンプルは語ります。
「彼らは、私たちの健康状態を感じ取ります。肉体的な領域と精神的な領域のバランスが崩れたり、相対的世界に固執しすぎると、体のバランスが崩れます。どんな状況であっても、病気になるのです。シャーマンの所に行って癒しや浄化が必要だと言えば、吐き気や便意を催す薬草をくれます。まずは浄化して、それだけで肉体と精神のバランスを取り戻せるかを試すのです。
シャーマンにこの薬草のことをドラッグだと言えば、『それは全然違う』と答えるでしょう。『それは君たちの世界観の思いこみだ』と。この薬草はニューワールドのモノであって、異次元世界をつなぐ植物だから、『聖なる』植物として扱わなければならない。サボテンを鍋に入れて何時間も煮込んでいる間に、効果を高めるために良い気を入れることが重要だ。なぜなら、私たちは今世代の聖なる植物の番人だからです。この伝統を継承しているからです。だからこの伝統を尊敬し、大切にしましょう」
私たちはただの「思いこみ」で、何千年も続いてきた伝統を安易に壊したり、否定します。
しかし、「ならば私たちの文明は本当に正しいのか」と言えば──全くもって、そうではありません。
きっとこのペルーの地では、鬱病になった人に対して「大量の薬」が処方されることはないでしょう。
いえ、それどころか鬱病にさえかかることがないかもしれない。その事実だけで、充分「私たちの文明の問題点」が分かるような気がしてきます。
巡礼を前に、ワシューマと呼ばれる飲み物を飲んで儀式を行います。そうすることで、その地の自然との繋がりが強くなるからです。
原住民やシャーマンといった人々は、「いかに人間にとって、自然との繋がりが大切か」を知っている人たちのように思います。
それは「生命の本質」に近い在り方であって、エゴによって自然を支配しようとしている文明人の在り方とはほど遠い。いわば、「共存共栄」であり「調和しあう姿勢」だと、私には思えます。
そうした彼らの在り方を見ると、「文明というものは、人間の進化の産物と呼べるのか」──私は疑問です。
技術が便利になったところで、生物が退化してしまえば「まったくもって意味がない」。明らかに、私たち先進諸国の人たちは肉体的な意味でも、また精神的な意味でも退化してしまっているのではないでしょうか。
シャーマンや原住民の生き方は、私たちに「これからの人類は、どのように自然と共に生きていけばよいのか」という問題を提議してくれている──そんなふうにも感じる次第です。
DVD「地球巡礼者」絶賛発売中。(すでにお持ちの方は、これからの解説も踏まえて視聴して頂けましたら幸甚です。何度みても必要なメッセージが、この中に含まれている──私はそう感じました。)
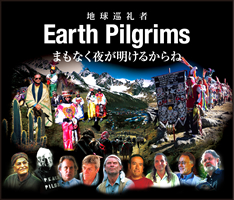
エハン・デラヴィ最期のトークイベントも受付中です。
17年間の研究成果すべてを聞けるラストチャンスです。

YOU are EARTH 篠崎由羅
2010年03月08日
地球巡礼者─アースピルグリム─(2)人間の欲望──聖なる執着
こんにちは、YOU are EARTHの篠崎です。前回に引き続き、「地球巡礼者─アースピルグリム─」の解説を致します。
「巡礼」という名を出せば、大抵引き合いに出されるのは「エルサレム」でしょう。
私は子供時代からイエス・キリストを尊敬していたので(注※実家は浄土宗なので、まったく無縁ですが)、いつかは必ず行ってみたい──そう思える場所でした。
しかし、今やその面影は人々の小競り合いによって、打ち消されてしまった──映画「アースピルグリム」の中に出てきた聖職者達の争いを見て、溜息を吐きたくなったのは私だけではないはずです。
何故、あのように聖地が奪い合われるようになったのか──そもそも「キリスト教」「ユダヤ教」「イスラム教」の違いが分からない方もいらっしゃるのではないかと存じます。
最初にあったのは「ユダヤ教」です。旧約聖書を中心に教えを説くのがユダヤ教であり、その教えは「ノアの方舟」や「バベルの塔」「モーセの十戒」など、どことなく戒めを感じさせるものも多く、今で言う「慈愛」とはほど遠い印象も受けます。
その後に誕生したのは「キリスト教」。しかし、イエス・キリストは最初からユダヤ教を批判していたわけではなく、教義主義に陥っているファリサイ派(パリサイ派という記載もあり)の人々の姿勢を批判していたに過ぎません。イエスが求めたのは「純粋な神への信仰」であり、それは供物や寄付などとといった物質に頼るものではなかったからです。何故そう言えるのか──それは、イエス自身が「自らの身を十字架に捧げた」ことが象徴しています。
そして、西暦に入ってから500年前後に誕生したのが「イスラム教」です(もっとも、イスラム教の巡礼はメッカ((現在のサウジアラビア))も主流ですが)。
これは、当時商人だったムハンマドが瞑想中、ガブリエル(アラビア語読みはジブリール)から啓示を受け、そこから派生しました。ムハンマドは当初自分が発狂したのではないかと苦悩しましたが(ムハンマドはとても堅実で、まじめな人柄だったそうです)、彼の口から語られる言葉の多くが人々の感動を呼び起こし、まずは家族が彼の言葉を受け入れ、そのうちに周囲へと波及し、イスラム教へと発展していったそうです。
ですので、言ってしまえばこの三つの宗教は「兄弟」のような関係性でもあるのです。それが何故か、今のような事態となってしまった──。
ユダヤ教にしろ、キリスト教にしろ、イスラム教にしろ、「最初は本当に、純粋な神の言葉だったのだろう」私はそのように感じています。
しかし、何故今のような現状を引き起こしたかと言えば──それはひとえに「聖なる執着」。
「アースピルグリム」で語られていた通り、「エルサレムが最も聖地であるという執着が生み出したが故の結末」だと、私には思えるのです。
私は、映画の中にあったメッセージに、強く心を揺さぶられました。
人間同士の戦争や対立が、神の御名に対する見解の違いから起こっている。
なんと愚かなことだろう。
争いを望む者はおらず、全員が友好の長いテーブルへの着席を待っているというのに……。
称えるのはひとつ。
賛美すべきはただひとつ。
巨大な鉢の中へ水差しの水を注ぐように、
すべての宗教と神に捧げる歌はひとつの歌。
違いはただの幻に過ぎないのだ。
太陽の光は反射する壁によって……まったく違って見えることもある。
それでも、同じ光なのだ。
私たちは太陽の光から衣服と、時空の中にある個性を借りているにすぎない。
神を超える時光を、反射しているのだ。
この言葉は、「ひとつの神」という存在に背を向け争い続ける愚かな人類を端的に述べている──そう私は思います。
親にとって、愛すべき子に差別などない。
どの子供だって、みな等しく愛すべき存在なのに、かたや子供同士は「やれ自分の方が愛されている」「やれ、お前の信じている親は本当の親じゃない」──そんなことを言って争っているのと大差はないのですから。
しかし、だからといって「どの子供の言っていることが正しい」なんていうことでもありません。言ってしまえば、「誰もが正しく、誰もが間違っているのかもしれない」。それはひとえに「視点の角度」が違うだけの話でしかないのだろうと、私にはそう思えるのです。
ある人はそのものを見て「これは円だ」と主張し、ある人は「違う! これは三角形だ」と主張したとしましょう。
でも、真実の姿は「円錐」であったとしたら──どうでしょうか?
下から見上げればそれは円にしか見えず、横から見れば「三角形」に見える。
どちらの言っていることも「正しくて」、ある一方では「間違っている」。
今起きている宗教観の争いも、実はそんな単純なものなのかもしれません。
インドの「バガヴァッド・ギータ」に、このような言葉が書かれていると、サティシュ・クマールが紹介しています。
「すべては、自分のものではない。それぞれが自らに属し、宇宙は宇宙に属している。
自分は宇宙の一部に過ぎない。すべての苦しみや悩みは「執着心」から生まれます。」
私の子供。
私のお金。
私の家。
私の夫。私の家族。
私のもの。
所有という概念が「如何に争いを呼び起こすのか」が、端的に示されています。
所有が、本当の平和を生み出すことはあり得ません。
それに神は、「所有して欲しい」などと願うものでしょうか?
愛する子にものを授け、「お前だけが特別に使いなさい」なんて言うでしょうか?
その真実に気づけるまで、まだまだ人類は試行錯誤を続けなければならないとしたら──何とも愚かな話ですね。
巡礼が産んだ──望ましくない結果。
あまりにも哀しすぎる顛末です。
サティシュ・クマールが、この章をこのような言葉で締めくくっています。
「第二のアイデンティティは切り捨てましょう。
日本、アメリカ、イギリス、インド、中国などの国籍ではなく、
『人間というアイデンティティ』を、大切にしましょう。」
果たして私たちは、「人間としてのアイデンティティ」を大切にして生きて来れたのでしょうか?
決して「そうではない」ということは、もう皆さんが歴史の中で学んで来たことだと思います。
そして、今もそれはすでに進行中です。
では、ここから先私たち人類の前に立ちはだかるものは何なのか──これは次回、ご紹介します。
DVD「地球巡礼者」絶賛発売中。(すでにお持ちの方は、これからの解説も踏まえて視聴して頂けましたら幸甚です。)
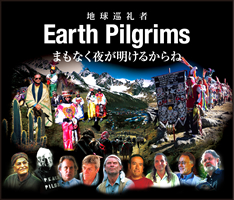
エハン・デラヴィ最期のトークイベントも受付中です。
17年間の研究成果すべてを聞けるラストチャンスです。

「巡礼」という名を出せば、大抵引き合いに出されるのは「エルサレム」でしょう。
私は子供時代からイエス・キリストを尊敬していたので(注※実家は浄土宗なので、まったく無縁ですが)、いつかは必ず行ってみたい──そう思える場所でした。
しかし、今やその面影は人々の小競り合いによって、打ち消されてしまった──映画「アースピルグリム」の中に出てきた聖職者達の争いを見て、溜息を吐きたくなったのは私だけではないはずです。
何故、あのように聖地が奪い合われるようになったのか──そもそも「キリスト教」「ユダヤ教」「イスラム教」の違いが分からない方もいらっしゃるのではないかと存じます。
最初にあったのは「ユダヤ教」です。旧約聖書を中心に教えを説くのがユダヤ教であり、その教えは「ノアの方舟」や「バベルの塔」「モーセの十戒」など、どことなく戒めを感じさせるものも多く、今で言う「慈愛」とはほど遠い印象も受けます。
その後に誕生したのは「キリスト教」。しかし、イエス・キリストは最初からユダヤ教を批判していたわけではなく、教義主義に陥っているファリサイ派(パリサイ派という記載もあり)の人々の姿勢を批判していたに過ぎません。イエスが求めたのは「純粋な神への信仰」であり、それは供物や寄付などとといった物質に頼るものではなかったからです。何故そう言えるのか──それは、イエス自身が「自らの身を十字架に捧げた」ことが象徴しています。
そして、西暦に入ってから500年前後に誕生したのが「イスラム教」です(もっとも、イスラム教の巡礼はメッカ((現在のサウジアラビア))も主流ですが)。
これは、当時商人だったムハンマドが瞑想中、ガブリエル(アラビア語読みはジブリール)から啓示を受け、そこから派生しました。ムハンマドは当初自分が発狂したのではないかと苦悩しましたが(ムハンマドはとても堅実で、まじめな人柄だったそうです)、彼の口から語られる言葉の多くが人々の感動を呼び起こし、まずは家族が彼の言葉を受け入れ、そのうちに周囲へと波及し、イスラム教へと発展していったそうです。
ですので、言ってしまえばこの三つの宗教は「兄弟」のような関係性でもあるのです。それが何故か、今のような事態となってしまった──。
ユダヤ教にしろ、キリスト教にしろ、イスラム教にしろ、「最初は本当に、純粋な神の言葉だったのだろう」私はそのように感じています。
しかし、何故今のような現状を引き起こしたかと言えば──それはひとえに「聖なる執着」。
「アースピルグリム」で語られていた通り、「エルサレムが最も聖地であるという執着が生み出したが故の結末」だと、私には思えるのです。
私は、映画の中にあったメッセージに、強く心を揺さぶられました。
人間同士の戦争や対立が、神の御名に対する見解の違いから起こっている。
なんと愚かなことだろう。
争いを望む者はおらず、全員が友好の長いテーブルへの着席を待っているというのに……。
称えるのはひとつ。
賛美すべきはただひとつ。
巨大な鉢の中へ水差しの水を注ぐように、
すべての宗教と神に捧げる歌はひとつの歌。
違いはただの幻に過ぎないのだ。
太陽の光は反射する壁によって……まったく違って見えることもある。
それでも、同じ光なのだ。
私たちは太陽の光から衣服と、時空の中にある個性を借りているにすぎない。
神を超える時光を、反射しているのだ。
この言葉は、「ひとつの神」という存在に背を向け争い続ける愚かな人類を端的に述べている──そう私は思います。
親にとって、愛すべき子に差別などない。
どの子供だって、みな等しく愛すべき存在なのに、かたや子供同士は「やれ自分の方が愛されている」「やれ、お前の信じている親は本当の親じゃない」──そんなことを言って争っているのと大差はないのですから。
しかし、だからといって「どの子供の言っていることが正しい」なんていうことでもありません。言ってしまえば、「誰もが正しく、誰もが間違っているのかもしれない」。それはひとえに「視点の角度」が違うだけの話でしかないのだろうと、私にはそう思えるのです。
ある人はそのものを見て「これは円だ」と主張し、ある人は「違う! これは三角形だ」と主張したとしましょう。
でも、真実の姿は「円錐」であったとしたら──どうでしょうか?
下から見上げればそれは円にしか見えず、横から見れば「三角形」に見える。
どちらの言っていることも「正しくて」、ある一方では「間違っている」。
今起きている宗教観の争いも、実はそんな単純なものなのかもしれません。
インドの「バガヴァッド・ギータ」に、このような言葉が書かれていると、サティシュ・クマールが紹介しています。
「すべては、自分のものではない。それぞれが自らに属し、宇宙は宇宙に属している。
自分は宇宙の一部に過ぎない。すべての苦しみや悩みは「執着心」から生まれます。」
私の子供。
私のお金。
私の家。
私の夫。私の家族。
私のもの。
所有という概念が「如何に争いを呼び起こすのか」が、端的に示されています。
所有が、本当の平和を生み出すことはあり得ません。
それに神は、「所有して欲しい」などと願うものでしょうか?
愛する子にものを授け、「お前だけが特別に使いなさい」なんて言うでしょうか?
その真実に気づけるまで、まだまだ人類は試行錯誤を続けなければならないとしたら──何とも愚かな話ですね。
巡礼が産んだ──望ましくない結果。
あまりにも哀しすぎる顛末です。
サティシュ・クマールが、この章をこのような言葉で締めくくっています。
「第二のアイデンティティは切り捨てましょう。
日本、アメリカ、イギリス、インド、中国などの国籍ではなく、
『人間というアイデンティティ』を、大切にしましょう。」
果たして私たちは、「人間としてのアイデンティティ」を大切にして生きて来れたのでしょうか?
決して「そうではない」ということは、もう皆さんが歴史の中で学んで来たことだと思います。
そして、今もそれはすでに進行中です。
では、ここから先私たち人類の前に立ちはだかるものは何なのか──これは次回、ご紹介します。
DVD「地球巡礼者」絶賛発売中。(すでにお持ちの方は、これからの解説も踏まえて視聴して頂けましたら幸甚です。)
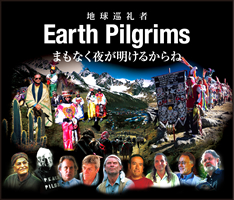
エハン・デラヴィ最期のトークイベントも受付中です。
17年間の研究成果すべてを聞けるラストチャンスです。

2010年03月06日
地球巡礼者─アースピルグリム─(1) 公案について
こんにちは、YOU are EARTHの篠崎です。
先日、これから「エハンさんの著作に関する解説をご紹介する」旨お知らせしましたが、第一回目のシリーズは「地球巡礼者─アースピルグリム─」をいくつかのカテゴリーに分けてご紹介します。
私がこの作品を拝見した際、正直に受けた感想は「この作品の本当の意味や良さを、果たして日本人のどれだけ多くの人が理解出来るのだろうか」という疑問でした。
それは決して、日本人を卑下してのことではありません。
日本の国土の条件、民族性、歩んできた歴史、あらゆるものをトータルし踏まえた上での感想だったのです。
巡礼者という言葉は、どうしたところで定住者の人に理解しがたい言葉です。
映画作品に出てきた空海にしろ芭蕉にしろ、彼らは多くの土地を歩み、その中でさまざまな体験を経て研鑽を積み上げた人達です。そうした体験がなければ、すぐさま巡礼という言葉に馴染めない──そう考える人も多いのではないでしょうか?(勿論、ここで言われている巡礼というのは「定住云々」という表層的な意味ではないのですが、それは後日、違う記事で解説します。)
日本は「島国」です。勿論イギリスだって島国ではありますが、バイキングという「海の移住者達」を背景にもった国と「最初から土着していた国の特性」とはやはりどうしたところで差があります。
また、黄色人種の特色や白人の特色による「歴史的な差違」が日本の独特な風習を生み出した可能性もあるでしょう。
日本は「島国」であり、かつ「江戸時代まで鎖国していた」という様々な要素、および第二次世界大戦を経て「アメリカの文化を人真似のごとく取り入れるしかなかった」という条件も踏まえた中で、どうしたところで「地球巡礼者」という映画の意味を理解しづらい民族性なのではないか──そのように私は感じたのです。
また、エルサレムを中心とした宗教紛争に関しても、日本人は「他人事」のように思ってしまう人が多いかもしれません。
それは、決して日本人が「冷たい」と言っているわけではありません。学校教育の中で「宗教や哲学、思想」というものをしっかり教えてこなかったことが原因の一端だと私は感じています。私は哲学科出身故、倫理や思想史を中心に学んできましたが、それだって「ごくごくさわりの部分だけ」です。世界史における倫理や思想史における割合は本当にごく僅かで、順当に学校教育を経た人であればイスラムの宗教史、キリストの宗教史を知っている方がごく僅かであっても「無理はない」──そのように思えるのです。
日本の学校教育は「高い偏差値」を取る為だけにあって、本当のこころの教育をする為のものではなかった──そうした弊害が、様々な形で、今日本に押し寄せているのかもしれません。
その為、この映画作品は日本人にとって「理解しがたいもの」になってしまう面も否定は出来ない──そう私は思いました。
でも、本来この映画で語られているのは「遙かに深淵で壮大なテーマ」なのです。
この作品の中には「今、日本人に必要な答えが『描かれている』」私はそう感じました。
いえ、それは日本に限ったことではなく、世界中のすべての人に言えることなのかもしれません。
私たちは既存システムにおける限界のすれすれに立たされているにも関わらず、それでもなお、「従来のやり方」でそれを無理矢理型にはめようとしています。
それでは「何も解決しないのだ」ということを、「地球巡礼者─アースピルグリム─」では語っています。
私たちがこの追い詰められた状態の中で「何を、どうすればいいのか」──その答えは「公案にある」、この映画ではそう語られています。
公案というのは「禅公案」のことです。
馴染みのない方の為に簡単に説明しますと、日本における禅には道元の開いた「曹洞宗」と白隠の「臨済宗」(実際日本に持ち込んだのは栄西ですが、江戸時代に再度臨済禅を白陰が立て直してからの方が有名になった関係で白隠禅とも呼ばれています)の二者があります。
禅公案を元に行うのは後者の「臨済宗」です。曹洞宗では「何も言わず、ただ座る(黙照禅)」ことを目的にし、対して臨済宗では「看話禅」といって、公案を掘り下げることを目的としています。
もっとも、そんな呼び名は「どうでもいい」ことであって、曹洞宗にしろ臨済宗にしろ「目先だけの現実を超え、その向こう側に答えを求める」という姿勢は共通している──私はそのように感じています。
要するに、「目先だけの損得、利潤、合理的な考え方では、『もう何も解決しないところまで来ているんだ』」ということを、私たちはまず何よりも自覚すべきなのではないでしょうか。
社会が行き詰まっているのも、国が行き詰まっているのも、誰が悪いわけでもなく──「私達、個々人にだって責任があるのだ」と、私はそう思えるのです。
なら「どうすればいいのか」?
それは、「私たちひとりひとりが導き出すべきもの」であり、誰かに教わったりすがって導いてもらうものではないのでしょう。
それこそが「独立個人の本当の意味」であり、私たちが向かおうとする時代にとって最低必要条件なのかもしれません。
余談ですが。
「思考を突き詰めれば、やがて認識の壁にぶち当たってしまう。そして、その壁を越えられた時にこそ、私たちは自分達を束縛していた殻をつきやぶることが出来るのかも知れない」──多少言葉を変えていますが、人智学(アントロポゾフィー)で有名なルドルフ・シュタイナーも同じように言っています。
彼が禅を体験していたかどうか定かではありませんが、「認識できる現象を超えたところにこそ、答えがある」ということを、同じように彼も知っていたのかもしれません。
DVD「地球巡礼者」絶賛発売中。(すでにお持ちの方は、これからの解説も踏まえてさらに視聴して頂けましたら幸甚です。)
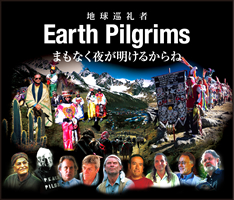
エハン・デラヴィ最期のトークイベントも受付中です。
17年間の研究成果すべてを聞けるラストチャンスです。

先日、これから「エハンさんの著作に関する解説をご紹介する」旨お知らせしましたが、第一回目のシリーズは「地球巡礼者─アースピルグリム─」をいくつかのカテゴリーに分けてご紹介します。
私がこの作品を拝見した際、正直に受けた感想は「この作品の本当の意味や良さを、果たして日本人のどれだけ多くの人が理解出来るのだろうか」という疑問でした。
それは決して、日本人を卑下してのことではありません。
日本の国土の条件、民族性、歩んできた歴史、あらゆるものをトータルし踏まえた上での感想だったのです。
巡礼者という言葉は、どうしたところで定住者の人に理解しがたい言葉です。
映画作品に出てきた空海にしろ芭蕉にしろ、彼らは多くの土地を歩み、その中でさまざまな体験を経て研鑽を積み上げた人達です。そうした体験がなければ、すぐさま巡礼という言葉に馴染めない──そう考える人も多いのではないでしょうか?(勿論、ここで言われている巡礼というのは「定住云々」という表層的な意味ではないのですが、それは後日、違う記事で解説します。)
日本は「島国」です。勿論イギリスだって島国ではありますが、バイキングという「海の移住者達」を背景にもった国と「最初から土着していた国の特性」とはやはりどうしたところで差があります。
また、黄色人種の特色や白人の特色による「歴史的な差違」が日本の独特な風習を生み出した可能性もあるでしょう。
日本は「島国」であり、かつ「江戸時代まで鎖国していた」という様々な要素、および第二次世界大戦を経て「アメリカの文化を人真似のごとく取り入れるしかなかった」という条件も踏まえた中で、どうしたところで「地球巡礼者」という映画の意味を理解しづらい民族性なのではないか──そのように私は感じたのです。
また、エルサレムを中心とした宗教紛争に関しても、日本人は「他人事」のように思ってしまう人が多いかもしれません。
それは、決して日本人が「冷たい」と言っているわけではありません。学校教育の中で「宗教や哲学、思想」というものをしっかり教えてこなかったことが原因の一端だと私は感じています。私は哲学科出身故、倫理や思想史を中心に学んできましたが、それだって「ごくごくさわりの部分だけ」です。世界史における倫理や思想史における割合は本当にごく僅かで、順当に学校教育を経た人であればイスラムの宗教史、キリストの宗教史を知っている方がごく僅かであっても「無理はない」──そのように思えるのです。
日本の学校教育は「高い偏差値」を取る為だけにあって、本当のこころの教育をする為のものではなかった──そうした弊害が、様々な形で、今日本に押し寄せているのかもしれません。
その為、この映画作品は日本人にとって「理解しがたいもの」になってしまう面も否定は出来ない──そう私は思いました。
でも、本来この映画で語られているのは「遙かに深淵で壮大なテーマ」なのです。
この作品の中には「今、日本人に必要な答えが『描かれている』」私はそう感じました。
いえ、それは日本に限ったことではなく、世界中のすべての人に言えることなのかもしれません。
私たちは既存システムにおける限界のすれすれに立たされているにも関わらず、それでもなお、「従来のやり方」でそれを無理矢理型にはめようとしています。
それでは「何も解決しないのだ」ということを、「地球巡礼者─アースピルグリム─」では語っています。
私たちがこの追い詰められた状態の中で「何を、どうすればいいのか」──その答えは「公案にある」、この映画ではそう語られています。
公案というのは「禅公案」のことです。
馴染みのない方の為に簡単に説明しますと、日本における禅には道元の開いた「曹洞宗」と白隠の「臨済宗」(実際日本に持ち込んだのは栄西ですが、江戸時代に再度臨済禅を白陰が立て直してからの方が有名になった関係で白隠禅とも呼ばれています)の二者があります。
禅公案を元に行うのは後者の「臨済宗」です。曹洞宗では「何も言わず、ただ座る(黙照禅)」ことを目的にし、対して臨済宗では「看話禅」といって、公案を掘り下げることを目的としています。
もっとも、そんな呼び名は「どうでもいい」ことであって、曹洞宗にしろ臨済宗にしろ「目先だけの現実を超え、その向こう側に答えを求める」という姿勢は共通している──私はそのように感じています。
要するに、「目先だけの損得、利潤、合理的な考え方では、『もう何も解決しないところまで来ているんだ』」ということを、私たちはまず何よりも自覚すべきなのではないでしょうか。
社会が行き詰まっているのも、国が行き詰まっているのも、誰が悪いわけでもなく──「私達、個々人にだって責任があるのだ」と、私はそう思えるのです。
なら「どうすればいいのか」?
それは、「私たちひとりひとりが導き出すべきもの」であり、誰かに教わったりすがって導いてもらうものではないのでしょう。
それこそが「独立個人の本当の意味」であり、私たちが向かおうとする時代にとって最低必要条件なのかもしれません。
余談ですが。
「思考を突き詰めれば、やがて認識の壁にぶち当たってしまう。そして、その壁を越えられた時にこそ、私たちは自分達を束縛していた殻をつきやぶることが出来るのかも知れない」──多少言葉を変えていますが、人智学(アントロポゾフィー)で有名なルドルフ・シュタイナーも同じように言っています。
彼が禅を体験していたかどうか定かではありませんが、「認識できる現象を超えたところにこそ、答えがある」ということを、同じように彼も知っていたのかもしれません。
DVD「地球巡礼者」絶賛発売中。(すでにお持ちの方は、これからの解説も踏まえてさらに視聴して頂けましたら幸甚です。)
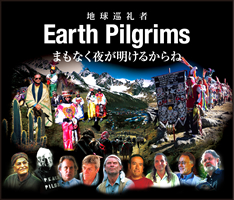
エハン・デラヴィ最期のトークイベントも受付中です。
17年間の研究成果すべてを聞けるラストチャンスです。

2009年12月18日
2009年09月12日
Tokyo Roadshow and quiz
正解です!
echan@echan.jp
date Sat, Sep 12, 2009 at 11:35 AM
subject Where am I?
hide details 11:35 AM (19 hours ago)
こんにちは。
もう誰かが先に回答していると思いますが、メールしてみました。
答えは、イスラエル死海北西の都市「クムラン」です。

Where am I? Signed book present to the first correct respondent!
東京に行く日は増えて来たが毎回は楽しみだ。お時間があれば是非ともご参加を!
2009年9月12日(土)
開場 18:20
開始 19:00~
アネモネ主催
「エハン・デラヴィ」トークセッション
&映学「アースピルグリム」上映会
★当日、エハン・デラヴィさんからのトークセッションがあります★
590名入る劇場型の観賞しやすい会場です。
・日時:2009年9月12日(土)
・会場:練馬文化センター 小ホール(東京都練馬区練馬1-17-37)
西武池袋線・西武有楽町線・都営地下鉄大江戸線 練馬駅北口より徒歩1分
・参加費:前売3,500円 当日4,000円(各税込)
・定員:592名
・スケジュール
18:20 開場
19:00 ご挨拶
19:05~19:45 エハンさんトークセッション
19:55~21:25 映学「アースピルグリム」上映
・お申込方法
郵便局へお振込ください。
口座番号:00170-0-555907 加入者名:アネモネ
郵便お振込をもちまして申込完了となります。当日、受付にて半券(振込票兼受領証)をチケット扱いとして回収いたしますので、必ずご持参ください。
必要な方はあらかじめコピー願います。
払込取扱票の通信欄に「アースピルグリム上映会」とご記入ください。
・お問合せ先 03-5436-9200 (株)ビオ・マガジン
echan@echan.jp
date Sat, Sep 12, 2009 at 11:35 AM
subject Where am I?
hide details 11:35 AM (19 hours ago)
こんにちは。
もう誰かが先に回答していると思いますが、メールしてみました。
答えは、イスラエル死海北西の都市「クムラン」です。

Where am I? Signed book present to the first correct respondent!
東京に行く日は増えて来たが毎回は楽しみだ。お時間があれば是非ともご参加を!
2009年9月12日(土)
開場 18:20
開始 19:00~
アネモネ主催
「エハン・デラヴィ」トークセッション
&映学「アースピルグリム」上映会
★当日、エハン・デラヴィさんからのトークセッションがあります★
590名入る劇場型の観賞しやすい会場です。
・日時:2009年9月12日(土)
・会場:練馬文化センター 小ホール(東京都練馬区練馬1-17-37)
西武池袋線・西武有楽町線・都営地下鉄大江戸線 練馬駅北口より徒歩1分
・参加費:前売3,500円 当日4,000円(各税込)
・定員:592名
・スケジュール
18:20 開場
19:00 ご挨拶
19:05~19:45 エハンさんトークセッション
19:55~21:25 映学「アースピルグリム」上映
・お申込方法
郵便局へお振込ください。
口座番号:00170-0-555907 加入者名:アネモネ
郵便お振込をもちまして申込完了となります。当日、受付にて半券(振込票兼受領証)をチケット扱いとして回収いたしますので、必ずご持参ください。
必要な方はあらかじめコピー願います。
払込取扱票の通信欄に「アースピルグリム上映会」とご記入ください。
・お問合せ先 03-5436-9200 (株)ビオ・マガジン
2009年06月25日
本の紹介

あとがき ― 未来の巡礼者たち
狐には穴ぐらがあり、空の鳥には巣があるが、人の子には頭を休める場所はない
-イエス・キリスト
突如として二〇一二年の情報があふれかえっている。多数の本も出て、二本のハリウッド映画がもうすぐ公開されるし、世界中のニュース記事が、この出来事の不気味な重要性を仰々しく指摘している。現在のこのような予兆は、時間に関する高度な視点を持っていたマヤ文明に結晶化された古代の予言とスムースに溶け合っていく。マヤ文明は基本的にこのことを僕タイに遺している ― 今、人類は世界の終焉の時代に生きている。一九九三年以来このことについて語り、日本にこの情報をもたらした責任がある者としては、この十六年後という「タイミング」にも 驚いていない。
最近、週刊プレイボーイでさえも、二〇一二年の特集記事を載せたくらいだ。若い女性の美しい体の写真の間に挟まれた記事は、多少場違いな感じがしたことは否めないが……。宇宙のユーモアも健在という感じだ。これはまさに一般の人のレベルで、文字通り二〇一二年のことを裸にしてみんなに見せるという意味だったのだろう。同誌の記者は僕にいろいろ関係する質問をした。ただ、ひとつ言っておかなければならないのは、彼らは同じ質問をすでに四年前にしていたということだ。そのときは、当然ながら編集部もこれを掲載することに躊躇し、結局日の目を見なかった。今はそれほど懐疑的ではないようである。二〇〇九年の現在、低俗なレベルの「実現しなかったノストラダムスの予言」との比較では、きちんとした情報を持つ日本人には通用しないということなのかもしれない。
人々はもっと真剣な問いかけをしているようである。現在の金融危機が、これまで見ようとする人がほとんどいなかったタブーの扉を、わずかながらやっとこじ開けたように見える。この世界的な混沌と古代の預言ははたしてつながっているのだろうか。ヨーロッパのシンクタンク、ブダペスト・クラブの所長で、著名なシステム理論の哲学者であるアーウィン・ラズローでさえ、僕の最初の著書『マージング・ポイント』のテーマと共鳴する『カオス・ポイント』という本を出している。一九九三年ごろにはまったく異端の考えだったものが、大衆文化の中に劇的な再登場を果たし、しかもそこには二〇一二年十二月二十一日、冬至の日という、避けられない日付までついてきているのだ。ラズロー博士は、このカオス・ポイントの「ブレークスルー(画期的)か、ブレークダウン(破壊)か」というテーマを真剣に捉えており、「ワールド・シフト」という名の世界的な組織を設立することまでしている。
しかし、論理的に考えれば、頑固な否定論者が言うように、「空騒ぎ」であることもありえるのだろう。世界の縫い目がほころび始めているように見えるのも単なる偶然かもしれない。二〇一二年は、ほとんど説明のつかない世界経済の崩壊の前例のないスピードとは、まったく関係ないことだってあり得るではないか。いったい僕たちはどう考えたらいいのか。生態系から経済まで、あらゆるセクターにわたるグローバルな崩壊を目撃しているのか。それともこれは単なる不景気の繰り返しなのか。すべては単なる偶然なのだろうか。これまで何度も勇敢にやってきたように、僕たちはいろいろやって何とかこの危機をくぐり抜けられるのだろうか。
一歩立ち止まり、この表面的には偶然と見えるものについて、単なる好奇心以上のものをもって考慮してみなくてはならないのは間違いない。古代の歴史に埋もれた終末論の預言の真の意味が体に浸透してくるにつれて、二〇一二年なんてばからしいという条件反射の反応はしにくくなるかもしれない。このような考えが笑い飛ばされていたわずか数十年前でさえ、この地球には、今はもうない、豊かな資源があふれていたということを忘れないようにしよう。たとえば石油、そして真水だ。当時は、無限とも思えるこのような資源があった。今日の駆け足で進んでいくストレスだらけの生活ではなく、みんなもっと自分の時間があったように感じられないだろうか。そして、もちろん地球上の人口も今よりはずっと少なかった。
to be continued....