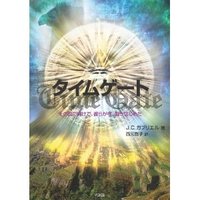2011年06月28日
Jaguar death

ガブリエルのビジョンには、大きなジャガーが登場していた。
獰猛さを振りまき、彼の周囲をゆっくり旋回しながら、獲物を目掛けて大きな口で近寄ってきた。まずい!殺されてしまう!そう確信した。この恐ろしいネコ科の動物は、しなやかに動きながらも、本当に容赦なく人を傷つけるのだ。
「ダイダイダイダディーダイダイダダ、ダイディーディーダイディーデデダ!」
酔いしれるようなチャンティングの声が、ジャングル全体を包み込む。ドンの魂は、時を超えて熱帯に吹く涼しい風のように一行の間をすり抜けながら漂っていた。
ジャガーは、ガブリエルの顔をめがけて力強く右足から飛び掛かって来た。その足先の鋭い爪が、月夜の中でギラリと光った。不思議なことに、すべての色は、ここの次元では、全く違った色彩に見える。それぞれの色は、まるで息づいているかのように鮮やかだ。ガブリエルは、最初の一撃で顔を引き裂かれた瞬間、スローモーションの動きの中で、その長い恐怖を味わっていた。
「さあ、今度は、その顔をぐちゃぐちゃにしてやろうかな?どうだね?」
ジャガーがテレパシーで会話をしてきた。獲物を狙ってうなり声を上げるジャガーの身体全体からは、とてつもないパワーがオーラのように発光している。ガブリエルは、心の内で絶叫に近い悲鳴を上げているはずなのに、彼の口は、すでに引き裂かれ、目玉もえぐられており、鼻や口と共にジャングルの血の海の中に転がっているのだった。
ドンの柔らかく軽快なメロディは、だんだんとボリュームが上がってきた。虹虎の泣き声もピークに達し、もはや呼吸困難になりながら、嗚咽にならない声を絞り出している。
虹虎を受け取った修道女は、彼を院内のベビーベッドに寝かしつけた。まだ赤子でしかない虹虎ではあったが、この時、ここからもう2度と出られないという絶望感を悟っていた。もう母親は決して戻ってこない。そんな失望の念が、小さな体の血管の中をぐるぐると巡っている。
天ノ山は、ぼんやりと虚ろな目でテーブルの足元を見つめていた。
自分が殺ってしまった男と過ごした日々が走馬灯のように駆け巡る。バカなことを言い合ってはふざけあったこと、義理と人情の任侠の世界で、盃を交わした舎弟として彼を可愛がったこと、やらねばならない“仕事”がつまづいたときには、叱咤激励の意味を込めて懲らしめたことなどが頭の中を行き来していた。
そして、もう決して会うことはない大阪にいる彼の娘と息子のこと。妻は暴力が耐えなかった夫との地獄のような暮らしから、やっと今、自由になっているのだろうか。
ドンの“イカロ(聖なる歌)”と呼ばれるシャーマンの歌声がだんだんと大きくなってくるにつれ、天ノ山の頭の中では、それらすべての出来事が畳み掛けるように襲い被さってきていた。
「ダイダイダディー、ダイダイダダイ、ダダデイ・・・」
「メアリー・・・、ちょっと、起き上がるのに手を貸してくれないか」
メアリーは、そのスペイン語の声に反応すると、すぐに立ち上がった。
その夜のガブリエルには、下腹の丹田のあたりでベルを鳴らしているような音がずっと聞こえていた。メアリーは肩にかけていたショールを素早くはずすと、足元がふらついている彼の腕を掴んで木の側に連れていった。
彼は、すでにこちらの世界に戻ってきてはいるものの、ジャングルを取り囲むエネルギーの波や光の渦などの内なるビジョンに、まだ圧倒されっぱなしだった。
突然、彼は座り込んだ。次の瞬間、肛門から次々と身をくねらせやってくる赤いヘビを外に放った。あまりのことに、あたふたとトイレットペーパーをなんとか掴み、苦しさにうめきながらメアリーに一人にしてくれと頼むのがやっとだった。彼は、これがあのジャガーからの次なる攻撃だとわかっていた。
今、ガブリエルが体験していることは、当然起こりえることであるとメアリーは頭ではわかっていた。けれども、その様子をいざ実際に見るとなると、一気に引いてしまうのだった。
彼女は、ドン・イグナチオの歌が今やピークを迎えている一行の輪の中に、ゆっくりと戻っていった。
ガブリエルは、ジャングルの森の中でも“樹木の王様”と呼ばれ、小枝から葉の天辺から幹の部分まで木陰を作ってくれる木にしなだれかかって、ズボンを穿きながら、ヨタヨタともたついていた。彼の排泄物は、足元を汚してしまっていた。
その時、ビジョンの中に、再びジャガーの姿が入ってきた。そこには、顔のついていない生き物がいた。次の一撃は、致命傷を与える決定的なものだった。大きな衝撃と共に、太ももに生暖かいぬめっとしたものが落ちてきた。
気づくと、それは自分の内臓だった。なんと、ジャガーの喉元からむき出しになっている象牙色の牙で、胴体が噛みちぎられてしまったのだ。
もう、体中がずたずただ。この顔のない生き物は、単に獰猛に見えながらも、したたかなことに、きちんと計算して襲ってくる。
さらに、最後に息の根を止めようとして、頚椎を目掛けて飛び掛ってくる。その、ガブリとかじる音が聞こえた瞬間、顔はないものの、キラリと光った冷静沈着な目が見えた気がした。それは、自分をすべてから解き放った目だ。それは“愛”そのものだった。
Posted by エハン at 06:00
│Timegate