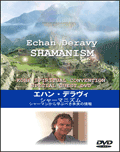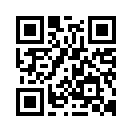2008年02月11日
禅文化との出会い
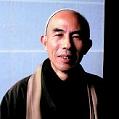
小堀南嶺老師
一番惹かれたのは、やはり京都だった。大阪は商人の町で肌に合わなかった。
大徳寺には、英語の上手な老師がいた。小堀南嶺老師。この人は英語で禅の講演をしていたの
だけれど、一目で素晴らしい人物だとわかった。
それで、定期的に座禅会に参禅するようになった。
回りには禅に興味をもって勉強しに来ている外国人がたくさんいた。アメリカ人が多かったけれど、
だいたい2種類に分けられた。一つは公案を好むタイプ。これは非常に知的なユダヤ人の友だち
に多いタイプだった。要するに頭を使いたがるわけだね。もう一つは、曹洞宗を選ぶタイプ。
これは、頭を使わない「只管唯坐」に憧れる。さすがに臨済宗と曹洞宗。よく出来ていると思った。

道元禅師
僕はどちらにも属さなかった。グループ活動はあまり好まないのだね。だから、自分の家で
座禅した。毎朝5時に起きて2時間。隣の部屋にいたアメリカ人の友だちと一緒に40分の座禅と
10分の経行(きんひん)を繰り返すのだ。経行とは、きわめてゆっくりと、まるで止まっているかの
ように静かに歩くことだ。これは正式な参禅のやり方と変わらない。そうやって精神世界の修行し
ながら、昼は英会話の仕事に行っていたのだった。
日本の芸術や文化にどっぷり浸かっていたのは、僕だけではなかった。
例えば友だちの中には、能面を彫る天才的なアイルランド人がいた。彼の生活ぶりはハンパじゃなかった。京都北部の花背という村で能面の先生について、毎日何時間も徹底的に能面彫りを習っていた。茅葺の家に住みこんで、日本人にも負けないほどの腕前だった。いわゆるガイジンの東洋趣味じゃないんだ。本気で日本の伝統文化を学ぼうという志がなければ、とても無理なことだった。
毎朝5時間座禅するニューヨーク出身のボクサーもいた。彼はニューヨークに戻ったときに、本物の豆腐づくりをやった。日本デザインと仏教を研究していた友だちは、その後チベットのラマ層になった。おそらく最も有名な外国のラマですよ。修道院で7年間修行したテキサスのお坊さんもいた。墨絵に没頭している人もいたし、英語と日本語の両方で俳句を作るユダヤ人の友だちもいた。彼の漢字能力はケタ外れだったね。
充実したカルチャーライフだった。でも、日本で再びの禅ライフを継続する前に、「旅病」が疼きだした。〝うーん、京都もいいけど、ここにじっとしていられない。メキシコ、中南米、ボリビアが俺を呼んでるー〟って感じがしてきた。
こうなると、僕はもう駄目だった。旅人は動いてないとストレスがたまる。1975年3月、バンクーバー経由で、サンフランシスコ、メキシコ、ボリビアへの旅に出た。再び世界放浪の旅に出たのだ。日本での長い修行をするために先ず6ヶ月間の旅が要求されたのだ。帰ってきた後で十数年間日本から一歩もでなかった!
Posted by エハン at
11:48
│Autobiography