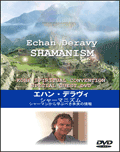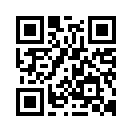2007年12月23日
「お遍路さんですか?」

「7回目といっても、まだまだ修行足りないですから。会社勤め以外の自分の時間は、お遍路する
ことにしてるんです」
僕は心底感動した。普通、1回やれば十分なのに、7回なんて。ハンパなことじゃない。もう本当の
修行だと思った。現代の修行者に会った気がした。どこまでやっても、究めたということがない。
伝統的日本人の姿だと思った。
「洗心」という言葉が浮かんだ。僕も歩いているから、彼のプロフェッショナルな魂がよくわかる。
巡礼のプロとはこういう人なのだ。日本はやはり美しい国だね。そういう思いが湧いてきていた。
しかし、一方で気になることがあった。とにかく若い人の姿が見えないし、人気がなさすぎる。誰が買
うのか、流行遅れの古い洋服が2000円で売られている。店には誰もいない。村全体に活気がない。
一番合理的な説明として考えられるのは、みんな家にこもってテレビを見ているということだった。
外出すれば金もかかるし、必要以上の買い物はしないのだろう。四国は経済的にかなり苦しいのだ。実際に、地元の人から聞かされたときはショックだった。
「あんた、地元じゃ毎月の生活費どのくらいやと思う? 17万円ですよ。それで子供を学校に行か
せて生活せんならん」
たった17万円。僕は言葉もなかった。活気などあるわけないんだ。古くて懐かしい日本の風景はゴーストタウンだったのだ。経済的に苦しければ、雰囲気は暗くなるのは当たり前だ。毎月一回、
4泊5日のお遍路をしながら、四国のダークな部分に気づきだしたのは、徳島県を抜け、高知県を
歩いていた秋から冬にかけてのことだった。
冬になれば、お遍路の姿も少なくなる。だからといって宿は閉じられない。一人の僕のために、営業
していてくれる。それでたった5000円だ。この大変さ、わかりますか。めちゃめちゃきついことですよ。
地元の人は、お遍路さんにそれほどのシンパシーを持っていないようにさえ感じた。僕の経験では、
8割以上の農家の人は、お遍路を無視している。むしろ、〝お遍路なんて、宗教くさいことようやるわ。なんや格好つけて……。こっちはそんな余裕ないわ〟という感じなのだ。これははっきり伝わってきた。特に働き盛りの世代は、そういう雰囲気を醸し出している。当然でしょうね。みんな生活するのに精一杯なのだ。
歩くほうも必死、生活してるほうも必死。非常に重苦しい波動を感じ始めていた。
ただ、爺ちゃん、婆ちゃんは違った。この人たちは、この土地でずっと農業やってきて、70年、
80年、苦労を重ねてきた人たちだ。お遍路のつらい事情もわかるのだね。道で出会うと、必ず頭を
下げて、「ご苦労様です」と言ってくれる。中には、「ちょっと待ってな」と、桃などの特産フルーツを
わざわざ持ってきてくれたりする。
あるときには、軽自動車が停まって、おばちゃんが降りて近づいてきた。
「お遍路さんですか?」
はいと答えると、おばちゃんは、どうぞと言って、アイスクリームをくれた。たぶんアイスクリームの
商売をやってる人だったんでしょう。でも、見知らぬ外人相手に、アイスクリームだよ? はあー、
日本人はすごいなあと思った。感激した。こういうところで、人を疑わないのだ。心から素晴らしいと
思う。もし、イギリスにお遍路があったとしても、頭も下げないし、ご苦労様なんて声をかけたりしないだろう。単に怪しまれるだけだ。僕が、日本に「人間に対する基本的な信頼が残っている」というのはこういうことなのだ。お遍路さんに対する「お接待」と呼ばれる行為なのだけれど、封筒に千円とか三千円とか入れて渡してくれる人もいるのだ。
「冷たいものでも飲んでね」
Posted by エハン at
09:40
│Autobiography